税理士コラム
小学生の頃の体験活動による将来の効果
- 投稿日:2022年07月20日
文部科学省による「21世紀出生児縦断調査」を活用した体験活動の効果等の分析結果が発表されました。それによると、小学生の頃に体験活動(自然体験・社会体験・文化的体験)や読書、お手伝いを多くしていた子どもは、その後、高校生の時に自尊感情(自分に対して肯定的、自分に満足している)や外向性(自分のことを活発だと思う)、精神的な回復力(新しいことに興味を持つ、自分の感情を調整する、将来に対して前向き)といった項目の得点が高くなる傾向がみられたということです。
| 体験活動 | 自然体験(キャンプ、登山、川遊び、ウィンタースポーツなど)、社会体験(農業体験、職業体験、ボランティア)、文化的体験(動植物園・博物館・美術館見学、音楽・演劇鑑賞、スポーツ観戦など)に分けて分析すると、
自然体験 → 主に自尊感情や外向性、
に良い影響が見られることが分かった |
|---|---|
| 読書 | 読書を多くすると、新奇性追求(新しいことに興味を持つ)や感情調整(自分の感情を調整する)、肯定的な未来志向(将来に対して前向き)といった精神的な回復力や、向学校的な意識に良い影響が見られることが分かった |
| 遊び | 異年齢の子どもや家族以外の大人など多様な相手と遊ぶ機会が多いと、自尊感情や外向性などに良い影響が見られることが分かった |
| お手伝い | お手伝いを多くすると、自尊感情や外向性、精神的な回復力、向学校的な意識などすべてに良い影響が見られることが分かった |
さらに、子ども成長は家庭環境の要因も影響することが考えられますが、家族構成、収入、住環境、親のしつけを考慮して体験の影響を分析した結果、小学校の頃に体験活動などをよくしていると、それらの家庭の環境に関わらず、その後の成長に良い影響が見られるということが分かりました。
「収入格差が教育格差に繋がっている」という話はよく耳にしますし、そういう側面もあるだろうと思います。しかし、今回の調査結果によると、収入の水準が相対的に低い家庭にいる子どもであっても、例えば、自然体験の機会に恵まれていると、家庭の経済状況などに左右されることなく、その後の成長に良い影響が見られるということです。
- カテゴリ:税理士コラム

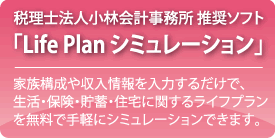
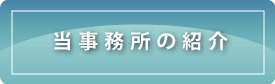





 0120-915-745
0120-915-745 zei@kobayashi-jp.com
zei@kobayashi-jp.com