税理士コラム
不動産売却は所有期間の判定に要注意! 短期譲渡の所得税額は長期譲渡の約2倍
- 投稿日:2022年11月22日
不動産の売却益にかかる譲渡所得税の税率は、売却した不動産の所有期間の長い不動産を売ったときのほうが、低い税率で課税される仕組みだ。
所有期間が5年以下の不動産を売却したときの譲渡所得は「短期譲渡所得」として税率は(復興特別所得税を考慮しないと)39%(所得税30%、住民税9%)。一方、所有期間が5年を超える不動産を売却したときは「長期譲渡所得」として税率は同20%(所得税15%、住民税5%)となる。
つまり、短期譲渡所得は、長期譲渡所得の約2倍の税金を納めなくてはならない。
不動産を売却するとき、所有期間が5年を超えるかどうかが重要なポイントとなる。そこで、特に注意が必要なのは、税金を計算する際の所有期間は、譲渡(売却)した年の1月1日時点で判断するということ。実際の所有期間とは違うのだ。
長期譲渡所得と認定されるには、「譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超えている」必要がある。
譲渡した年の1月1日における所有期間が5年以下だと、短期譲渡所得となる。税務上の所有期間は、売った年の1月1日時点にさかのぼって判断する。
売却した時点では所有期間が5年を超えていても、その年の「1月1日までさかのぼる」と5年に満たないことがあり得る。
所有期間の判断を誤ると、「税金を想定していた2倍も支払わないといけなくなった」ということになりかねない。所有期間の判断と売却のタイミングが重要になる。
わずか1~2ヵ月の違いで、税金を半分にすることができる場合もある。不動産売却は、税金対策の面からも、売却のタイミングが大事だ。
所有期間5年超の条件をクリアするには、取得した年に「6」を加えた年の1月1日より後に売却すること。そうすれば、税務上の所有期間5年超をクリアでき、長期譲渡所得の低い税率が適用できる。
所有期間が5年になる不動産物件は、年内でなく、年明けに売ると税金が安くなる。
- カテゴリ:税理士コラム
税理士コラム
源泉所得税等の納付期限と納期の特例 要件に該当しなくなった場合に注意!
- 投稿日:2022年11月02日
源泉所得税等の納付期限と納期の特例は、原則毎月の源泉所得税の納税を、納期の特例の適用を受ければ年2回で済ませることができるのだから、メリットは大きい。
しかし、注意点も少なくない。それは、給与の支給人員が常時10人以上となり、源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合は、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」の提出が必要となることだ。この届出書を提出した場合には、その提出した日の属する納期の特例の期間から所得税法第216条に規定する納期の特例の承認の効力が失われる。なお、適用要件を満たしていても、任意に納期の特例の適用を取りやめることも可能である。
また、会社を設立したケースでは、設立後すみやかに「納期の特例の承認に関する申請書」を提出していたとしても、設立した月の給与に関する源泉所得税等について納期の特例を適用することができない。納期の特例の適用を受ける前の源泉所得税は、原則どおり、支払った月の翌月10日までに納税しなければならない。これを忘れると、期限までに源泉所得税を納めなかったとして、不納付加算税が課される可能性があるため、注意が必要だ。
この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することが必要だ。この納期の特例申請書の提出先は、給与等の支払を行う事務所などの所在地を所轄する税務署長となっている。また、この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税等と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税等に限られている。
なお、源泉所得税の納期の特例の適用を受けることができるのは、給与等の支払を受ける役員や従業員などの人数が常時 10 人未満である源泉徴収義務者だが、ここでの「常時」とは、平常の状態を指している。つまり、繁忙時期に臨時に雇用して人数が増える場合は、その人数を除いて判断することになる。
- カテゴリ:税理士コラム

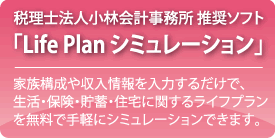
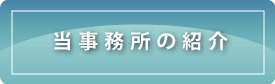





 0120-915-745
0120-915-745 zei@kobayashi-jp.com
zei@kobayashi-jp.com