税理士コラム
相続税の申告に必要な6つの手続きとは
- 投稿日:2023年06月21日
相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10ヵ月以内に行うことになっていますが、相続税の申告のためには、相続人の確認、遺言の有無、遺産と債務の確認、遺産の評価、遺産の分割など、以下の(1)から(6)の手続きが必要となります。
(1)「相続人の確認」は、被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せて相続人を確認する。
(2)遺言書があれば遺言書を開封する前に家庭裁判所で検認を受けるが、公正証書及び法務局に保管された自筆証書による遺言は検認を受ける必要はない。
(3)遺産と債務を調べてその目録や一覧表を作っておく。また、葬式費用も遺産額から差し引くので、領収書などで確認しておく。
(4)相続税がかかる財産の評価については、相続税法と財産評価基本通達により定められ一般に公表されているので、それらにより評価する。
(5)遺産の分割について、遺言書がある場合にはそれによるが、遺言書がない場合には、相続人全員で遺産の分割について協議をし、分割協議が成立した場合には、遺産分割協議書を作成する。なお、相続人のなかに未成年者がいる場合には、その未成年者について家庭裁判所で特別代理人の選任を受けなければならない場合がある。この場合、特別代理人が、その未成年者に代わって遺産の分割協議を行う。申告期限までに分割できなかったときは民法に規定する相続分で相続財産を取得したものとして相続税の申告をすることになる。
(6)相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10ヵ月以内に行うことになっている。なお、被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合の申告書の提出先、納税先はいずれも被相続人の住所地を所轄する税務署で、相続人の住所地ではない。
- カテゴリ:税理士コラム

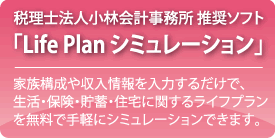
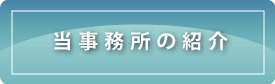





 0120-915-745
0120-915-745 zei@kobayashi-jp.com
zei@kobayashi-jp.com