税理士コラム
住宅取得資金贈与税の非課税制度は、メリットの多い長期優良住宅に注目!
- 投稿日:2023年05月17日
住宅を取得等する場合、
・2023年12月31日までの間に
・父母や祖父母などの直系尊属から
・自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を贈与してもらった場合
一定の要件を満たせば原則500万円の非課税枠がある贈与税の非課税制度
さらに
・省エネ性能や耐震性能、バリアフリー性能のいずれかで一定レベル以上の「省エネ等住宅」であることを証明できる場合
1000万円の非課税枠がある贈与税の非課税制度
があります。
省エネ等住宅であることの証明は、自身で新築するのであれば、設計の依頼をする段階で省エネ等住宅に該当する家を建てたいということを伝える必要があります。
500万円を超えて贈与を受けようとするなら、省エネ等住宅に該当する住宅を新築するか購入したほうがいいわけです。
省エネ等住宅に該当させるには、省エネ性能・耐震性能・バリアフリー性能のいずれかで一定の基準を満たせばいいのですが、長期優良住宅に認定されるには、加えて他の面でも一定の基準をクリアしなければなりません。
ちなみに、省エネ等住宅も長期優良住宅も、住宅ローンのフラット35で0.25%の金利優遇制度があります。
省エネ等住宅に該当すれば金利優遇期間が5年、長期優良住宅に該当すれば金利優遇期間が10年となっています。
長期優良住宅
省エネ等住宅も長期優良住宅も0.25%の金利優遇がありますので、ローン残高が多ければ多いほどそれなりの金額にはなりそうです。
長期優良住宅には、ほかにも地震保険料の割引、固定資産税・登録免許税の軽減制度や補助金制度もあります。
住宅は大きな買い物です。質のいい住宅を入手しようとするならば、かかる費用も多くなるため、贈与税の非課税制度を始め、色々な情報を整理して検討するとよいでしょう。
- カテゴリ:税理士コラム
税理士コラム
マイホームを売却したら損失が!どうなる?どうする?
- 投稿日:2023年04月20日
2023年12月31日までに住宅ローンのあるマイホームを住宅ローンの残高を下回る価額で売却して譲渡損失が生じたときは、一定の要件を満たすものに限り、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得との損益通算ができます。
さらに、損益通算をしても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年間繰越控除できます。
これらの特例を、特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例といいます。
特例適用の要件
特例適用の要件は、
自分が住んでいるマイホーム(譲渡資産)を譲渡すること
譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超えるマイホーム(譲渡資産)で日本国内にあるものの譲渡であること
譲渡したマイホームの売買契約日の前日において、そのマイホームに係る償還期間10年以上の住宅ローンの残高があること
マイホームの譲渡価額が❸の住宅ローンの残高を下回っていること
などがあります。
譲渡損失の損益通算限度額
特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例は、新たなマイホーム(買換資産)を取得しない場合であっても適用できます。
譲渡損失の損益通算限度額は、マイホームの売買契約日の前日における住宅ローンの残高から売却価額を差し引いた残りの金額が、損益通算の限度額となります。
例えば、購入代金6000万円のマイホームを2000万円で売却(譲渡損失4000万円)し、借入金残高が3000万円ある場合、「3000万円-2000万円=1000万円」が損益通算限度額となります。
なお、合計所得金額が3000万円を超える年がある場合は、その年のみ繰越控除が適用できませんので注意が必要です。
損益通算及び繰越控除の両方が適用できない場合
また、損益通算及び繰越控除の両方が適用できない場合があります。
それは、
親子や夫婦など特別の関係がある人に対してマイホームを売却した場合
マイホームを売却した年の前年及び前々年に、居住用財産の譲渡所得の3000万円の特別控除や居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率などの特例を適用している場合
マイホームを売却した年の前年以前3年以内の年において生じた他のマイホームの譲渡損失の金額について、特定のマイホームの譲渡損失の損益通算の特例を適用している場合
マイホームを売却した年またはその年の前年以前3年内における資産の譲渡について、マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の適用を受ける場合または受けている場合
などに該当する場合です。
- カテゴリ:税理士コラム

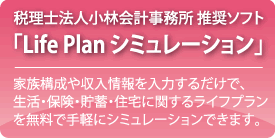
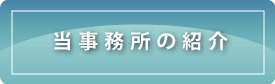





 0120-915-745
0120-915-745 zei@kobayashi-jp.com
zei@kobayashi-jp.com