税理士コラム
住宅取得等資金の贈与の新非課税制度
- 投稿日:2023年01月12日
父母や祖父母など直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置は、2022年度税制改正において見直されたが、国税庁ではこれを受けて、新非課税制度の周知を図っている。
見直しは、適用期限が2023年12月31日まで2年延長され、受贈者ごとの非課税限度額は、受贈者が新非課税制度の適用を受けようとする住宅用の家屋の種類に応じた金額とされる。
具体的な非課税限度額は、住宅用家屋の取得等に係る契約の締結時期にかかわらず、住宅取得等資金の贈与を受けて新築等をした住宅用家屋の区分に応じ、
(1)耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋は1000万円
(2)それ以外の住宅用家屋は500万円
とされる。
既に新非課税制度の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額となる。
注意点としては、新非課税制度等の適用を受ける人が、所得税の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン控除)を適用する場合において、(1)住宅借入金等の年末残高の合計額が、(2)住宅用の家屋の新築等の対価の額又は費用の額から、新非課税制度等の適用を受けた部分の金額を差し引いた額を超えるときには、その超える部分に相当する金額については住宅ローン控除の適用はないことが挙げられる。
新非課税制度は、贈与税の申告書の提出期間内に贈与税の申告書及び一定の添付書類を提出した場合に限り、その適用を受けることができる。
また、新非課税制度適用後の残額には、暦年課税にあっては基礎控除(110万円)を適用することができ、また、相続時精算課税にあっては特別控除(2500万円)を適用することができる。
なお、相続時精算課税を適用した金額は、贈与者が亡くなった時の相続税の課税価格に加算される。
- カテゴリ:税理士コラム
税理士コラム
成年年齢18歳に引下げに伴う税制改正 贈与税・相続税の年齢要件の違いに注意!
- 投稿日:2022年12月14日
民法の改正により、2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられた。
これに伴い、贈与税・相続税の規定における20歳を基準とする要件についても18歳に引き下げる税制改正が行われている。
国税庁は、改正の概要を紹介するパンフレットを公表し、贈与・相続等の時期によって、受贈者や相続人等の年齢に関する要件が異なっていることから、注意を呼びかけている。
贈与税では、原則60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子または孫に対し、財産を贈与した場合に選択できる「相続時精算課税」を始め、父母や祖父母などの直系尊属から、住宅の新築・取得または増改築等のための資金を贈与により受けた場合に、一定額までの贈与につき贈与税が非課税になる「住宅取得等資金の非課税等」、20歳以上の受贈者が直系尊属から財産の贈与を受けた場合の税率「贈与税の特例税率」、「相続時精算課税適用者の特例」の年齢要件が、2022年4月1日以降、その年1月1日において「18歳以上」となった。
また、相続税では、相続人が未成年である場合、成人するまでの年数に10万円を乗じた金額を相続税額から控除できる「未成年者控除」について、2022年4月1日以後に開始した相続に関しては、相続人が18歳未満の場合、18歳に達するまでの年数に10万円を乗じた金額が控除額となる。相続開始の時期によっては年齢要件及び控除額が異なるため留意したい。
同パンフレットでは、本改正に関するQ&Aを記載している。
Q1では、2022年3月に父から現金500万円の贈与を受けた受贈者が同年10月に19歳となる場合、この贈与について相続時精算課税の適用を受けられるかとの問いに対し、贈与の日は2022年3月31日以前であり、また、その年の1月1日において受贈者の年齢は18歳であるため、相続時精算課税の適用は受けられず、暦年課税により贈与税額を計算して申告することになると回答している。
- カテゴリ:税理士コラム

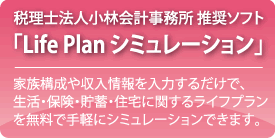
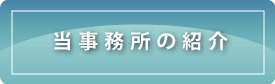





 0120-915-745
0120-915-745 zei@kobayashi-jp.com
zei@kobayashi-jp.com