税理士コラム
教育資金の一括贈与に係る非課税措置
- 投稿日:2022年02月24日
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置については、2年間延長されています。
| 現行 | 改正点 | ||
| 適用期間 | 令和3年3月31日まで | 令和5年3月31日まで | |
| 贈与者死亡時 | 相続税の課税対象 | 贈与から3年経過していれば管理残額は対象外 | 管理残額すべて(23歳未満や学生などは対象外) |
| 相続税の加算対象 | 孫などへの加算なし | 孫などへは2割加算 | |
※信託等があった日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合(ただし、死亡の日において、受贈者が①23歳未満である、②学校等に在学している、③教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している、いずれかに該当する場合は除く)、その死亡の日までの年数にかかわらず、管理残額を受贈者が相続等により取得したものとみなされる。
※上記により相続等により取得したものとみなされる管理残額について、贈与者の子以外の直系卑属に相続税が課税される場合、管理残額に対する相続税額が2割加算の対象となる。
- カテゴリ:税理士コラム
税理士コラム
ロボアドバイザーとは
- 投稿日:2022年02月07日
ロボアドバイザーのロボはロボット、アドバイザーは投資助言のことで、運用会社や証券会社などが、AI(人工知能)等を利用して、インターネットやアプリを通じて、投資助言や運用を提供するサービスのことです。
ロボアドバイザーは大きく分けると以下の2つに分けられます。
| 投資一任型 | リスク許容度などに合わせたポートフォリオを構築し、投資対象の選定から、発注、リバランスなどの実際の運用まで、全てお任せできる。 手間がかからず運用でき、専門知識がなくても始められる点がメリット。 |
|---|---|
| アドバイス型 | 運用についてのアドバイスのみ。投資商品の発注やリバランスなどの実際の運用は自分で行う。 ロボアドバイザーの助言を参考にして自分で考えて運用ができる。 |
ロボアドバイザーの最低投資金額や手数料は、各社サービスごとに異なっていますので、しっかり内容を確認した上で、利用するようにしてください。
- カテゴリ:税理士コラム

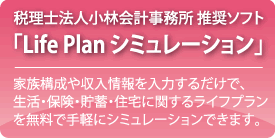
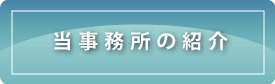





 0120-915-745
0120-915-745 zei@kobayashi-jp.com
zei@kobayashi-jp.com