税理士コラム
株式の譲渡所得申告漏れに注意
- 投稿日:2024年05月22日
国税庁は、株式公開買い付け(TOB)の成立で上場廃止となった株式に関し、譲渡所得の申告漏れが目立つことから、注意を喚起しています。
TOB成立後、上場廃止となった株式をTOBによる買付者などに買い取られた場合に譲渡益が生じたときには、所得税の申告が必要になります。なお、「譲渡益」とは、譲渡代金(買取価額)から取得費等を差し引いて計算した利益をいいます。
TOBは近年、上場企業に対するM&Aの手法として一般化しています。
国税庁は、TOBの買付総額が高額なものもあり、上場廃止後の株式譲渡に係る申告漏れの増加が懸念されたことから、株式を買い取った企業から税務署に提出されている「株式等の譲渡の対価の支払調書」(法定調書)に基づき、サンプル的に調査等を実施したところ、申告が必要であるにもかかわらず、申告漏れとなっているケースが多数把握されたとのことです。
無申告で追徴税額3000万円超えも!?
国税庁によると、TOBに応じなかった株主379人を対象に抽出調査した結果、約半数にあたる199人から申告漏れが見つかり、その申告漏れ所得金額は4億7495万円、追徴税額は7258万円で、申告漏れ1件当たりの追徴税額は36万円でした。
申告漏れが把握された事例の中には、1億8216万円と2億円近い多額の譲渡益が生じていたにもかかわらず、無申告となっていたものが含まれており、追徴税額3151万円が課されていました。
申告漏れの原因は「管理口座移動」
この申告漏れの背景には、株式を管理する口座が変わることにあります。
投資家の多くは、上場株式との取引を対象とする「源泉徴収ありの特定口座」を使っており、同口座は証券会社が売買損益や税額を計算して口座から天引きするため、投資家は自分で確定申告する必要がありません。
しかし、TOB成立で上場廃止となった企業の株式は、投資家自らが売買損益や税額を計算する「一般口座」での取引となり、利益が生じれば申告する必要があるのです。
株式公開買付(TOB)
公開買付者が、不特定かつ多数の者に対して買付期間・買付価格・買付予定株数などの公告等を通じて、証券取引所を通さずにそれらの株券等を株主から直接買い付けることをいいます。
TOBにおける買付価格は、市場の取引株価よりも高く設定されることが一般的です。企業を買収する場合や合併・子会社化など企業再編の際、またはMBO(経営陣による買収)で非上場化する場合などの際に用いられます。
- カテゴリ:税理士コラム
税理士コラム
金銭で支給されない経済的利益の取扱い
- 投稿日:2024年04月10日
給与所得とは、所得税における所得の区分の一つで、使用人や役員に支払う俸給や給料、賃金、歳費、賞与のほか、これらの性質を有する給与に係る所得をいいます。
また、青色事業専従者給与も、給与所得となる。役員や使用人に支給する手当は、原則として給与所得となります。
具体的には、残業手当や休日出勤手当、職務手当等のほか、地域手当、家族(扶養)手当、住宅手当なども給与所得となります。
しかし、例外として、
(1)通勤手当のうち、一定金額以下のもの
(2)転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるもの
(3)宿直や日直の手当のうち、一定金額以下のもの
のような手当は非課税となります。
例えば、通勤手当は、電車・バス通勤者の場合は1ヵ月当たり15万円までが非課税となり、マイカーなどで通勤している場合は1ヵ月当たりの非課税限度額が片道の通勤距離に応じて8段階で定められています。
給与課税されない「特定の現物給与」
また、給与は、金銭で支給されるのが普通ですが、食事の現物支給や商品の値引販売などのように、
(1)物品その他の資産の無償・低い価額での譲渡による経済的利益
(2)土地、家屋、金銭その他の資産の無償・低い対価での貸付けによる経済的利益
(3)福利厚生施設の利用など(2)以外の用役の無償・低い対価での提供による経済的利益
(4)個人的債務の免除または負担による経済的利益
をもって支給されることがあります。
これらの経済的利益を一般に現物給与といい、「特定の現物給与」については、課税上金銭による給与とは異なった特別の取扱いが定められています。
例えば、役員や使用人に、仕事に関係のある技術や知識を習得させるために支給する費用は適正なものであれば非課税であり、また、使用人に対して社宅や寮などを貸与する場合には、使用人から1ヵ月当たり一定額の家賃(「賃貸料相当額」)以上を受け取っていれば給与として課税されないこととされています。
一般に現物給与といわれる経済的利益は、原則として給与所得の収入金額とされますが、現物給与には、
(1)職務の性質上欠くことのできないもので主として使用者側の業務遂行上の必要から支給されるもの
(2)換金性に欠けるもの
(3)その評価が困難なもの
(4)受給者側に物品などの選択の余地がないもの
など、金銭による給与と異なる性質があり、また、
(5)政策上特別の配慮を要するものなど
もあります。
- カテゴリ:税理士コラム

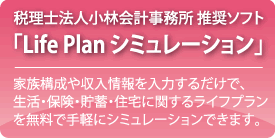
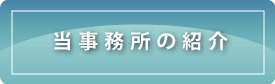





 0120-915-745
0120-915-745 zei@kobayashi-jp.com
zei@kobayashi-jp.com