税理士コラム
借地権、定期借地権等目的で異なる貸宅地
- 投稿日:2024年03月18日
貸宅地とは、借地権など宅地の上に存する権利の目的となっている宅地をいいます。
貸宅地の価額は、その宅地の上に存する権利の区分に応じて評価します。
まず、借地権の目的となっている宅地の価額は、「自用地としての価額-自用地としての価額×借地権割合」の算式で求めた金額により評価します。
この場合、借地権の取引慣行がないと認められる地域にある借地権の目的となっている宅地の価額は、算式の借地権割合を20%として計算します。
次に、定期借地権等の目的となっている宅地の価額は、原則として、その宅地の自用地としての価額から、定期借地権等の価額を控除した金額によって評価します。
ただし、それにより評価した金額が「自用地としての価額-自用地としての価額×定期借地権等の残存期間に応じた割合」の算式で求めた金額を上回る場合には、その算式で求めた金額を定期借地権等の目的となっている宅地の評価額とします。
上記の定期借地権等の残存期間に応じた割合は、
イ.残存期間が5年以下のものは5%
ロ.残存期間が5年を超え10年以下のものは10%
ハ.残存期間が10年を超え15年以下のものは15%
ニ.残存期間が15年を超えるものは20%
となります。
一般定期借地権の目的となっている宅地
また、定期借地権等のうちの一般定期借地権の目的となっている宅地については、課税上弊害がない限り、上記の方法によらず、一般定期借地権の目的となっている宅地の評価の方法により評価します。
一般定期借地権とは、借地の契約期間を50年以上として、代わりに、契約の更新や建物再築による期間の延長をしないなどの特約を付けることが認められる定期借地権契約のことです。
そのほか、定期借地権等のうちの一時使用目的の借地権の目的となっている宅地については、一時使用目的の借地権が雑種地の賃借権と同じように評価されることから、上記の方法によらず、「自用地としての価額-一時使用目的の借地権の価額」の算式により評価します。
地上権目的の宅地
地上権の目的となっている宅地の価額については、「自用地としての価額-自用地としての価額×相続税法第23条に定める地上権の割合」の算式で求めた金額により評価することとされています。
地上権とは、工作物または竹木を所有するために他人の土地を使用する権利とされています。
なお、建物の所有を目的とする地上権は借地権に含まれるので、ここでの地上権からは除かれることになります。
- カテゴリ:税理士コラム
税理士コラム
ストック・オプション、新株予約権の限度額を年3600万円に引上げ
- 投稿日:2024年02月16日
ストック・オプション(S・O)とは、会社が自社または子会社の従業員、役員等に対して付与する自社株式を一定の期間内にあらかじめ定められた権利行使価格で購入することができる権利をいいます。
資金が限られるスタートアップにとって、ストック・オプションは、優秀な人材を集める有効な手段として期待されています。
2024年度税制改正においては、そのストック・オプション税制が拡充されます。
具体案
具体的には、新株予約権の行使に係る権利行使価額の限度額について、設立の日以後の期間が5年未満の株式会社が付与する新株予約権については、その限度額を年2400万円(現行:年1200万円)に引き上げ、一定の株式会社が付与する新株予約権については、その限度額を年3600万円(現行:年1200万円)に引き上げます。
上記の「一定の株式会社」とは、設立後5年以上20年未満の株式会社で、上場等後の期間が5年未満であるものをいいます。
適用対象となる要件の見直し
また、中小企業等経営強化法施行規則の改正を前提に、適用対象となる特定従事者に係る要件の見直しを行います。
まず、認定新規中小企業者等に係る要件のうち「新事業活動に係る投資及び指導を行うことを業とする者が新規中小企業者等の株式を最初に取得する時において、資本金の額が5億円未満かつ常時使用する従業員の数が900人以下の会社であること」との要件を廃止します。
社外高度人材に係る要件
次に、税制の適用対象となる社外高度人材に係る要件について、「3年以上の実務経験があること」との要件を、金融商品取引所に上場されている株式等の発行者である会社の役員については「1年以上の実務経験があること」とし、弁護士や会計士など国家資格を有する者、博士の学位を有する者及び高度専門職の在留資格をもって在留している者については廃止します。
これによって、幅広い人材が確保しやすくなるのです。
社外高度人材の範囲については
(1)教授及び准教授
(2)金融商品取引所に上場されている株式等の発行者である会社の重要な使用人として、1年以上の実務経験がある者
(3)金融商品取引所に上場されている株式等の発行者である会社以外の一定の会社の役員及び重要な使用人として、1年以上の実務経験がある者
などが加えられ、スタートアップにおける外部の優秀な人材・協力者を集めやすくします。
- カテゴリ:税理士コラム

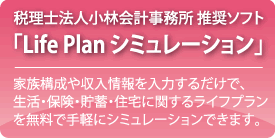
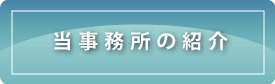





 0120-915-745
0120-915-745 zei@kobayashi-jp.com
zei@kobayashi-jp.com