税理士コラム
「タワマン節税」防止に新しい算定ルール
- 投稿日:2023年12月07日
国税庁は、マンションの相続税評価額について、市場価格との乖離の実態を踏まえた上で適正化を検討していた有識者会議の見直し案を公表しました。
この見直しの背景には、マンションの評価額が実勢価格の平均4割程度にとどまることから、その評価額の低さを利用したいわゆる「マンション節税」や「タワマン節税」が富裕層を中心に広がっていたことがあります。
そこで、相続税の新たな算定ルールを定め、その節税防止を狙います。
現行の相続等で取得した財産の時価
現行の相続等で取得した財産の時価(マンション(一室)の評価額)は、不動産鑑定価格や売却価格が通常不明であることから、建物(区分所有建物)の固定資産評価額と路線価等から計算した敷地(敷地利用権)の価額の合計額としています。
しかし、建物の市場価格は、建物の総階数やマンション一室の所在階、築年数が考慮されており、これらの反映が不十分だと、評価額が市場価格に比べて低くなるケースがあるのです。
また、マンション一室を所有するための敷地利用権は、共有持分で按分した面積に平米単価を乗じて評価されますが、この面積は一般的に高層マンションほどより細分化され狭小となるため、敷地持分が狭小なケースは立地条件の良好な場所でも、評価額が市場価格に比べて低くなります。
このように、建物の効用の反映や立地条件の反映が不十分なことが、マンションの相続税評価額と実勢価格の乖離の要因となっています。
見直し案
そこで、見直し案では、相続税評価額が市場価格と乖離する要因となっている
「築年数」
「総階数(総階数指数)」
「所在階」
「敷地持分狭小度」
の4つの指数に基づいて、評価額を補正する方向で通達の整備を行います。
具体的には、これら4指数に基づき統計的手法により乖離率を予測し、その結果、評価額が市場価格理論値の「60%」(一戸建ての評価の現状を踏まえたもの)に達しない場合は「60%」に達するまで評価額を補正することとします。
評価方法の見直しのイメージは、
(1)一戸建ての物件とのバランスも考慮して、相続税評価額が市場価格理論値の60%未満となっているもの(乖離率1.67倍を超えるもの)について、市場価格理論値の60%(乖離率1.67倍)になるよう評価額を補正
(2)評価水準60%~100%は補正しない(現行の相続税評価額×1.0)
(3)評価水準100%超のものは100%となるよう評価額を減額します
2024年1月からの適用を目指します。
- カテゴリ:税理士コラム
税理士コラム
貸宅地と貸家建付地
- 投稿日:2023年11月15日
賃貸アパートや賃貸マンションの敷地として利用している土地は、「貸家建付地」評価の対象となります。
貸家建付地に該当すれば、相続税評価額を減額できるため相続税を節税することが可能ですが、賃貸建物の敷地として利用している土地すべてが貸家建付地として評価できるわけではありません。
土地を他人へ貸している場合には「貸宅地」に該当しますが、貸宅地と貸家建付地では土地の評価額の計算方法が異なるので注意が必要です。
貸家建付地とは
貸家建付地とは、貸家の敷地の用に供されている宅地、すなわち、所有する土地に建築した家屋を他に貸し付けている場合の、その土地のことをいいます。
貸家建付地の価額は、
の算式で求めた金額により評価します。
この算式における「借地権割合」及び「借家権割合」は、地域により異なりますので、路線価図や評価倍率表により確認する必要があります。
また、「賃貸割合」とは、貸家の各独立部分がある場合に、その各独立部分の賃貸状況に基づいて、
により計算した割合をいいます。
この「各独立部分」とは、建物の構成部分である隔壁、扉、天井や床等によって他の部分と完全に遮断されている部分で、独立した出入口を有するなど独立して賃貸その他の用に供することができるものをいいます。
なお、継続的に賃貸されていたアパート等の各独立部分で、例えば、一定の事実関係(※1)から、アパート等の各独立部分の一部が課税時期(相続または遺贈の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)において一時的に空室となっていたにすぎないと認められるものについては、課税時期においても賃貸されていたものとして差し支えないこととされています。
※1 一定の事実関係とは、
(1)各独立部分が課税時期前に継続的に賃貸されてきたものである
(2)賃借人の退去後速やかに新たな賃借人の募集が行われ、空室の期間中、他の用途に供されていない
(3)空室の期間が、課税時期の前後の例えば1ヵ月程度であるなど、一時的な期間である
(4)課税時期後の賃貸が一時的なものではないこと
などで、これらのケースでは、課税時期においても賃貸されていたものとして認められます。
- カテゴリ:税理士コラム

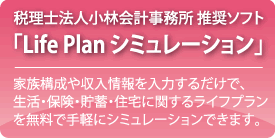
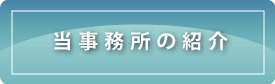





 0120-915-745
0120-915-745 zei@kobayashi-jp.com
zei@kobayashi-jp.com